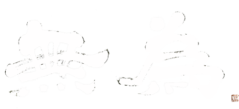Since 1968
上野焼宗家 渡窯
十二代 渡 仁 陶歴表
茶を千利休に、禅を大徳寺清厳に学び「茶禅一味」の奥義を極めた細川忠興。文禄・慶長の役で招致された李朝陶工・尊楷。
上野焼の歩みはこの二人の出会いから始まりました。
開窯に選んだ場所は陶土や原料に恵まれた上野。
1602年(慶長7年)、豊前藩主・細川忠興(三斎)は、尊楷を招いてこの地(釜の口窯)に築窯しました。尊楷は地名にちなんで上野喜蔵高国と名を改め、利休七哲の一人であった三斎好みの格調高い茶陶を献上し続けます。細川家の豊前統治は、肥後に移るまでの30年間と短いものでしたが、この間に上野焼の確固たる基礎が築かれたのでした。尊楷は藩主の移封(国替え)に従って、寛永9年(1632年)肥後熊本(八代)へ移りましたが、子の十時孫左衛門と娘婿の渡久左衛門が上野に残り、新藩主となった小笠原家のもと、皿山本窯で上野焼を継承していきます。
400年という悠久の歴史の中で,時代と共に趣を 変え洗練されてきた上野焼。その背景には、先人たちの計り知れない労が刻まれています。
渡窯、は現在、十二代 仁 により古くて新しい伝統を創り続けております。
Timeline
1968
上野焼宗家渡窯に生まれる
1993
東京造形大学彫刻科卒業
アジア周遊
1994
郷里 上野に戻り 父 久兵衛に師事
1998
西部工芸展入選 以後連続入選
2000
日韓若手作家交展開始 以降2009年まで10度開催
2007
日本陶芸展初入選
2010
日本工芸会正会員に認定
2012
西部伝統工芸展九州朝日放送賞受賞
上野焼宗家12代を継承